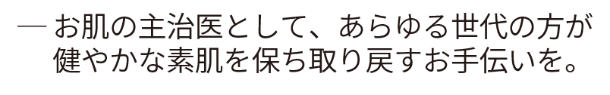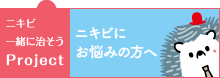花粉症の初期療法
毎年花粉症に悩まされ、原因も特定できているという方には、花粉の飛散前から治療をはじめる初期療法がお勧めです。症状を完全になくすことは難しいですが、症状が出る前に内服を開始することで
アレルギーへの過敏反応を抑制する
症状が出るのを遅らせる・軽くする
結果的にシーズンを通して内服する薬の量を減らせる
などの効果が期待できます。ただし、症状が落ち着いたからといって内服を中止してしまうと、薬の効果で抑制されていたアレルギー反応が出てきてしまいますので、シーズン中は医師の指示に従って治療を継続することが大切です。2~3週間前からの内服が効果的と言われていますので、原因となる花粉の飛散情報をチェックして、事前に医療機関を受診しましょう。
2015/01/14
花粉症検査はお済みですか?
間もなく春の花粉症シーズンがスタートします。関東では昨春の2~3倍花粉が飛散するとも言われておりますので、早めの対策で辛い症状を最小限に抑えましょう。花粉症には原因の特定と飛散時期に合わせた対策が有効です。こんなご症状でお悩みの方には採血によるアレルギー検査(花粉症検査)をお勧めします。
くしゃみや鼻水が止まらない
目や喉がかゆい
微熱や頭痛がある etc…
採血結果は1週間程度でわかります。もし花粉症と診断されてしまったら、原因となる花粉の飛散前に初期療法を開始して症状を和らげましょう。アレルギー検査では、花粉の他に食物や動植物・ハウスダストなどを組み合わせて最大13項目までお調べすることが可能です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
2015/01/14
本当は怖い低温熱傷
◆低温熱傷とは
湯たんぽやカイロ・ストーブ・ホットカーペットなど、通常なら受傷しない程度の低温熱源に長時間接触することで発生するやけどです。低温熱傷では、熱源に直接触れている部分は熱さや痛みを感じなくても、皮下組織が長時間に渡って損傷を受けている為、時間とともに損傷部分が壊死してしまいます。
◆低温熱傷の特徴
先程も述べたように、低温熱傷では受傷直後に痛みや熱さなどの自覚症状がなかったり、患部も軽い赤みや水疱ができる程度のことが多いです。1週間~10日ほどでようやく患部に痛みが出現する為、気づいた頃に医療機関を受診しても、すぐにはその後の経過を予測することができないのが特徴です。その為、根気よく通院し状況に適した治療を受けることが重要です。自己判断で放置すると、患部が細菌感染を起こしたり、傷跡が目立ちやすい状態で残ってしまう恐れもあります。
◆低温熱傷の予防
受傷してしまったら壊死を食い止めることはできない為、低温熱源との接触方法に留意する以外予防法はありません。就寝中の受傷が多い湯たんぽやホットカーペットは、使用時の温度が高くなり過ぎないようにしましょう。また暖房器具を使用する際は、同じ場所が長時間当たらないようご注意ください。自分の意思で自由に動くことのできない乳幼児や高齢者・身体の不自由な方には周りの方の配慮が必要です。
2015/01/08やけどの種類と応急処置
やけどの治りは受傷から数日のケアに掛かっていると言われ、特に受傷直後の応急処置は重要です。当院にも冬場は毎日のようにやけどの患者さまがいらっしゃいますので、やけどの種類と応急処置についてご案内いたします。
◆やけどの種類
やけどの重症度は深さと面積によって決まり、深度にはつぎの3種類があります。
| 症状 | 治癒までの期間 | 傷跡 | |
| 第1度熱傷 | 患部の発赤と痛み・熱感 | 数日 | 残りにくい |
| 第2度熱傷 | 患部の発赤や腫れと強い痛み・水ぶくれ・びらん・潰瘍など | 10日~2週間以上 | 残りやすい |
| 第3度熱傷 | 患部の壊死や乾燥・痛みを感じないことも | 1ヶ月以上 | 残る |
ひどいやけどで患部に痛みを感じないときは救急外来を受診してください。
やけどの部位や範囲など、場合によっては救急車を呼びましょう。
◆応急処置
水道の流水で痛みがなくなるまで15分程度冷やしてください。流水の出ないところでは保冷剤をあてたり、ペットボトルや水筒・コップに入った水やお茶をかけても構いません。とにかく 直ちに患部を冷やしてください。小さなお子さまや高齢の方は低体温を引き起こしやすい為、患部の冷やし過ぎにも注意して、氷嚢や保冷剤を当てる場合には必ずタオルを巻いて使用しましょう。
水疱が破れると感染症を引き起こしたり、痕が残ってしまう恐れもあります。破ったりつぶしたりしないよう気を付けましょう。水の勢いで破れてしまうこともありますので、流水をかけるときは患部から少しずらすようにしてください。熱湯を被るなどして衣服の上から受傷した場合には、無理に脱がせると皮膚が一緒に剥がれ悪化する場合がありますので、そのままの状態で衣服の上から冷やしてください。
医療機関を受診するまでの移動中も、濡らした清潔なタオルやガーゼ、またはタオルを巻いた氷嚢・保冷剤等を患部に当てて冷やしましょう。引き続き冷却が必要なケースもありますので、到着したら受付で「いつ・何が原因で受傷したのか」「どんな応急処置をどのくらいの時間行ったのか」をお伝えください。
2015/01/08帯状疱疹の患者さまが増えています
帯状疱疹は水疱瘡と同じウイルスが原因となって生じるもので、初めは身体の左右どちらかに刺すような痛みが生じ、そこに出来た赤い発疹が帯状の小さな水ぶくれとなることに病名が由来しています。
帯状疱疹は高齢者の方がかかる疾患と思われがちですが、子どもの頃水疱瘡にかかったことのある方なら誰にでも起こりうる可能性があり、日本では6~7人に1人がかかると推定されています。水疱瘡のウイルスは完治したあとも神経節と呼ばれる神経細胞が集まった部分に潜伏している為、過労やストレス・怪我・病気・加齢などさまざまな要因で身体の免疫力が低下すると復活し、帯状疱疹を発症します。季節の変わり目に発症することが多いとも言われており、寒さが厳しくなって当院を受診する患者さまも増えています。
無理をしたり適切な治療を受けずに放置すると重症化する恐れもありますので、ピリピリとした痛みや見慣れない発疹などの異常を認めたら、出来るだけ早く皮膚科におかかりください。
2014/11/25食物アレルギーについて
食物アレルギーとは、原因となる食物を摂取した際に自分の身体がそれを異物と認識し、防御の為に様々な反応を起こすことを言います。
主な症状として皮膚のかゆみやじんましんなどが挙げられますが、口腔内の粘膜が腫れることで呼吸困難に陥ったり、意識がなくなる・血圧が低下してショック状態になるといった命にかかわる重篤な症状を引き起こす場合もあり、注意が必要です。正確な数は把握できていませんが、全人口の約2%が何らかの食物アレルギーを持っていると考えられており、乳幼児期には鶏卵と牛乳が食物アレルギーの半数以上を占めますが、青年期に向かうにつれて甲殻類が増え、成人期以降には甲殻類の他に小麦・果物・魚介類が主な原因食品となります。食物アレルギーに対する有効な治療法はまだ確立されていない為、原因となる食物を特定し避けることが予防・治療を行う上で最も有効な手段といえます。
当院では採血によるアレルギー検査を行っておりますので、お心当たりのある方はどうぞお気軽にご相談ください。動植物やハウスダストなど、気になる項目と複数組み合わせての検査も可能です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
2014/11/06
季節に合わせたスキンケアを
衣替えの季節になりましたが、スキンケアの見直しはお済みでしょうか?
季節や天候によって変わるのは、服装だけでなくお肌の状態も同じです。当院では、異なった使い心地の保湿剤(ローション・クリーム・軟膏・他剤との混合など)をその時々の季節や状態に合わせて処方しています。日々移り変わるお肌に合わせて最適なケアができるよう、定期的な受診をお勧めします。まだまだ気になる日焼けあとや繰り返すニキビなど、お悩みのご症状もお気軽にご相談ください。
お肌のタイプに合わせたピーリングせっけんやシミに効果のあるクリーム、ビタミンCを配合したローション剤等も自費でお取扱いしています。ご興味のある方はスタッフまでお声掛けください。
2014/10/16
毛虫による皮膚炎
毎年春と秋にはチャドクガの幼虫をはじめとする毛虫が卵から孵化し、毛虫皮膚炎の患者さまが多くご来院されます。外遊びをするお子さまや庭木のお手入れをする方が被害に遭いやすいと言われていますが、お散歩コースや通学路にツバキ・サザンカなどの木がある方もこの時期は注意が必要です。
■毛虫皮膚炎とは?
毛虫の体を覆っている毒針毛が、何らかの原因で肌に付着することによって引き起こされます。特に被害の多いチャドクガは全身に約50万本もの毒針毛を持っている為、毛虫が好む木の下を通っただけで、風に飛ばされた毒針毛がついて皮膚炎になってしまうこともあります。
■症状
毒針毛に触れた部分に紅い発疹ができ、強いかゆみを伴います。毒針毛の長さは0.1㎜程度の為目には見えませんが、このとき患部を掻いてしまうと、発疹部分に刺さった毒針毛が手を介して周囲に広がり、発疹も広がってしまいます。症状が現れるのは腕や首回りといったお洋服の外に出ている部分が多いのですが、襟や袖口から毒針毛が入ると背中や腹部にも発疹ができてしまいます。
毒針毛に触れてから発疹が現れるまで時間差がある為、はじめは毛虫皮膚炎と気づかず掻いてしまい、症状を悪化させるケースも多いのですが、明らかに毛虫と接触した場合は決して患部をこすらず、粘着性のテープで毒針毛をはがし取ってからお水で洗い流してください。毒針毛が皮膚の奥に入ってしまうと完治まで数週間かかることもありますので、できるだけ早く皮膚科を受診し、つらいかゆみを抑えましょう。
2014/09/25日焼けもやけどの一種です
強い日差しをたくさん浴びて皮膚がヒリヒリ痛んだり、水ぶくれになった経験はありませんか?たかが日焼けと思っていても、それは立派なやけどです。
皮膚が赤く熱を持っている場合には、発熱や頭痛などの症状が見られる場合もありますし、水ぶくれができた場合には、やぶけたところから細菌が入ってしまうことも・・・このような症状が現れたら応急処置としてまず患部を冷やし、早めに皮膚科を受診してください。
日焼けしたお肌はシミの原因となったり、色素が沈着してしまう恐れもあります。また、水分も不足した状態になりますので、症状に合わせた外用薬・内服薬でしっかりケアしていきましょう。
2014/08/12とびひにご注意ください!
伝染性膿痂疹(とびひ)は、あせもや虫刺さされなどのひっかき傷から皮膚を溶かす毒素を持った細菌が侵入することによって、やけどのような湿疹が広がり、まるで火の粉のように自分や他人の身体に症状が飛び火する疾患です。
お子さまだけの疾患と思われがちですが、大人でも過労やストレスなどで免疫力が低下していると感染してしまいます。また、お顔や四肢など露出して手が届きやすい場所に出来ることが多く、強い痒みを伴うため、寝ている間に掻きむしって症状を広げてしまったり、そのまま放置すると跡が残ってしまう恐れもあります。症状に気づいたら、出来るだけ早めにご受診ください。
2014/07/25